今はインターネットで何でも調べることができることができます。
料理のレシピがわからないとき、スマホ片手でちょいちょいっと調べてみる。
お店の場所がわからないとき、スマホ片手にちょいちょいっと調べてみる。
体調不良の時、スマホ片手にちょいちょいっと考えられる原因を調べてみる。
歴史上の出来事を調べたいとき、スマホ片手にちょいちょいっと調べてみる。
スマホでもパソコンでもどちらでもよいのですが、一昔前では考えられないほどの進歩です。
さて本題です。
このようなネット社会において、わざわざ、相談料を払ってまで弁護士に相談する意味なんてあるのでしょうか。
弁護士のような専門家は、一般の方との情報格差を武器に「商売」をしています。
知らないこと、知らない解決策を知っているから、相談にきてもらえると。そのような関係です。
この情報格差が、ネット社会の登場によって、一気に崩れています。
そんなことぐらい俺でも知っている、ネットで見てみたら~と書いてあった。
だから専門家に聞きに行くまでもないと。そういうことになってしまう。
専門家受難の時代ともいえますし、
一億総専門家、誰もが専門家になれる素晴らしい時代がきたともいえるでしょう。
弁護士業界もその直撃を受けている業界のひとつだと思います。
弁護士に相談するのは敷居が高いなどといわれていたのも今は昔。
今は気軽に相談できる専門家の変わりとしてインターネットが登場しました。
弁護士に相談するまでもなく、インターネットで調べただけで、とりあえず用が足りてしまうこともある。
やはり弁護士はいらないのか。
もちろん、そんなことありません(我田引水といわないで。。)
ここで、見落としがちなのは、
インターネットなどで流通している情報は、あくまで一般論においては正しい回答であっても、それがあなたのケースで本当に正しい回答かどうかはわからないという点です。
通常、弁護士が相談を受けて、回答を導くまでの思考回路というものは、
(1)一般論(原則論)としては~~~であるが、
(2)しかし、あなたのケースの場合、☓☓☓という個別の事情がある。
(3)従って、結論としては、□□□となる可能性が高い。
という形で、一般論を踏まえ、さらに個別事情を踏まえた上で、回答を導き出すというものです。
ところが、ネット上のQ&Aなどの情報は、往々にして、あなたのケースにおける個別事情(☓☓☓)を考慮した上での回答になっていないのですね。
「この回答は、あくまで一般的回答をしているもので、必ずそうなるという結論を保証したものではありません」などというエクスキューズが入っていたりもしますね。
つまり、ネット上の法律相談に対する回答というものは、
弁護士が、自分の信用をかけて、専門家として、あなたに対して、あなたの個別的な事情をすべて考慮した上での、カスタマイズされた回答ではないのです。
もしかすると、それは、あなたにとって意味がない回答かもしれません(極論です)。
つまり、弁護士に相談をする意味というのは、
ネットに出回っている一般的回答が、あなたの個別的な事情をふまえたあなたのケースにおいても、妥当するものかどうなのか、そのズレについての答え(精度の高い解決への道筋)を得られるという点にあります。
このネット社会に顧問弁護士なんかいらないよ、なんて声をお聞きしますと、うん、たしかにそのとおりかもと一瞬同意しそうになることもなくはないのですが、
いやいや、意外と役に立てた場面だってあったではないかと、過去のお客様のお顔を思い出し、専門家受難時代でのささやかな抵抗のために、本日、この記事を書いた次第です。
ネット情報に負けないぞ!!(←魂の叫び)
ちなみに、どのような結論をとるにせよ、弁護士がやるべきこと、思考の流れはかわりません。
弁護士が一般論と同じ結論をとる場合であっても、一般論と異なる結論(見解)をとる場合であっても、
弁護士がすべきことは、
・あなたから広く、深く、掘り下げて事情を聴取して、その事情を分析すること。
・それをもとに、学説や判例の流れ、時代の趨勢、人間心理、当事者の置かれた状況などもすべてふまえたうえで、あなたのケースにおける結論(見解)を導くこと。
です。
弁護士によってこの力量にはかなりの差があります。
弁護士であれば、誰を顧問弁護士にしても同じというわけにはいかないのですね。










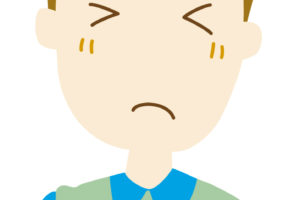



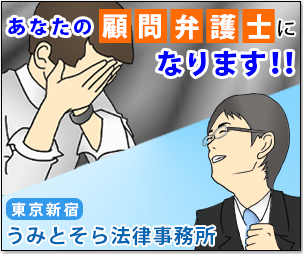
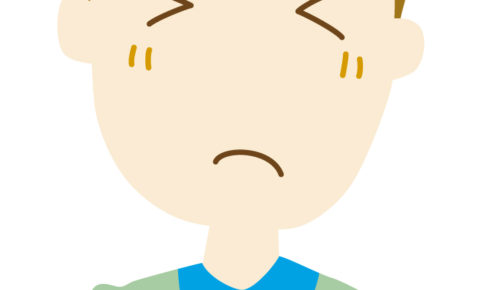



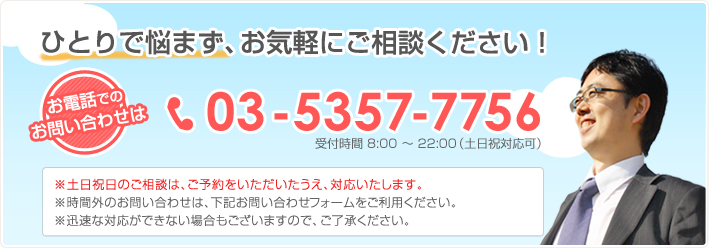
いや、非常にわかり易い文章ですね。お手本にしたい。
>ネット情報に負けないぞ!!(←魂の叫び)
これ面白いっす。
どもども。いつもありがとう!
私もいつも手本にしていますよ。
とても真似できないのだけど。。